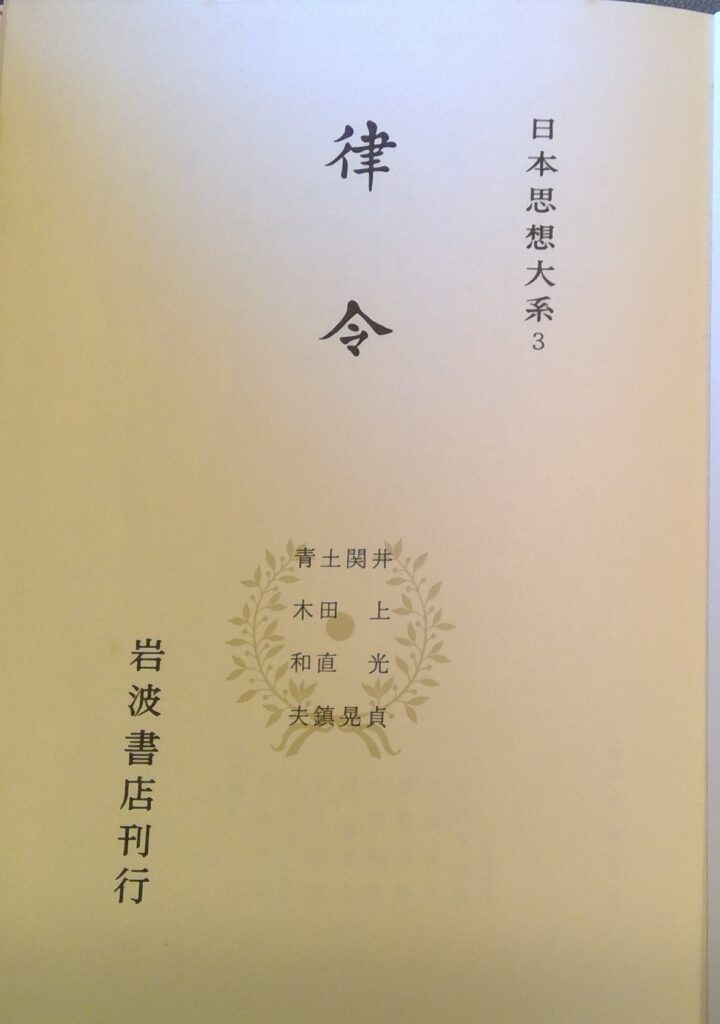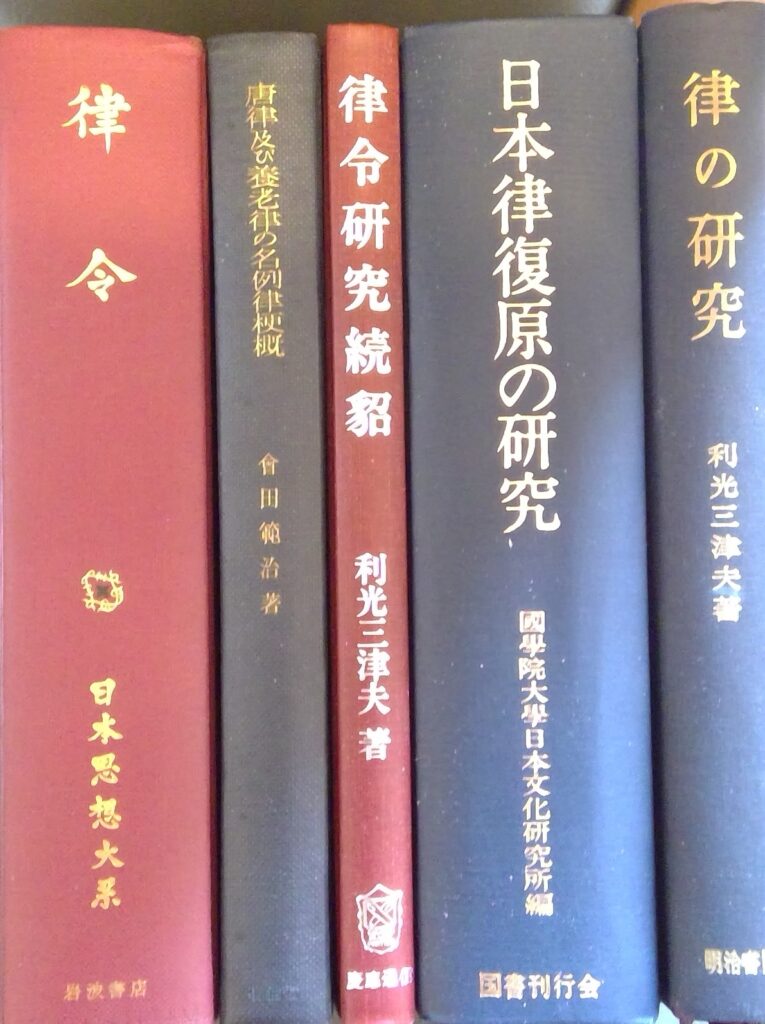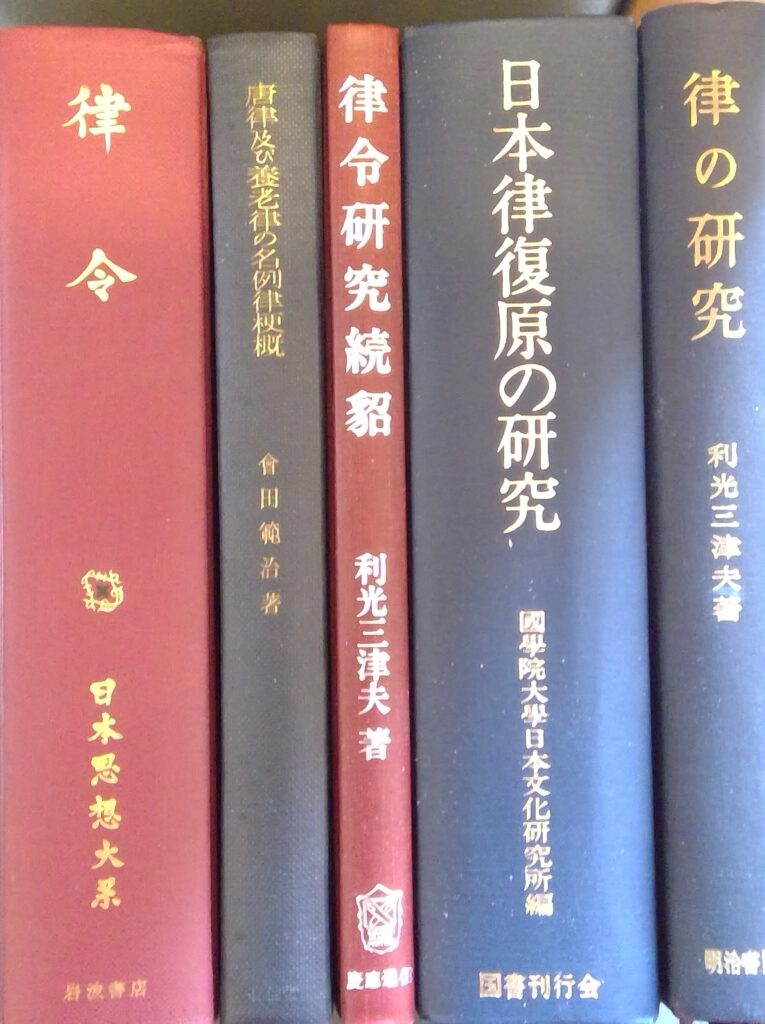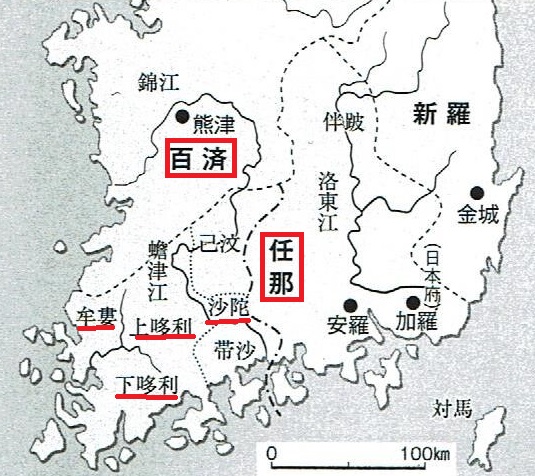養老律令の「職制律」は、まず主司(担当官)に対して法を曲げることを請託したが、賄賂の授受が行われていない場合を賄賂罪の基本形として定めています。
凡有所請求者、笞五十。(謂従主司求曲法之事。)〔謂凡是公事。各依正理。輙有請求。規為曲法者。〕[1](即為人請、与自請同。)〔謂為人請求者、雖非己事。与自請同。〕[2]主司許者、与同罪。〔謂然其所請之事者。〕[3](主司不許、及請求者、皆不坐。)〔謂主司不許曲法請求之人、皆不合坐。〕[4]乖已施行者、各杖一百。〔謂曲法之事已行。主司及請求之者、各杖一百。本罪仍在。〕[5]所枉罪重者、主司者、以出入人罪論。〔謂所司得属請枉断事。重於百杖者。主司得出入人罪論。假如先是一年徒罪。属請免徒、主司得出入徒罪。還得一年徒坐。〕[6]他人及親属為請求、減主司罪三等。〔若他人及親属為属請。免徒一年、減主司罪三等。唯合杖八十。此則減罪軽於已施行杖一百。如此之類皆依杖一百科之若他人親属等属請徒二年半罪。主司曲為断免者他人等減三等。乃合徒一年。如此之類。減罪重於杖一年者皆従減科。〕[7]自請求者、加本罪一等。〔謂身自請求、而得枉法者、各加所請求罪一等科之。〕[8]即監臨、勢要〔勢要者、雖官卑亦同。謂除監臨已外、田但是官人。不限官位高下。唯拠主司畏懼。不敢乘違者。〕[9]為人属請派者、杖一百。〔謂為人属請曲法者。無問行与不行。許与不許。但属即合杖一百。主司許者、笞五十。〕[10]所枉重者、罪与主司同。〔謂所枉重於杖一百。与主司出入坐同。〕[11]至死減一等。〔主司処法合死者。監臨勢要減死一等。〕[12]
【現代語訳】
主司(担当官)に対して法を曲げることを請託すれば、笞50回の刑に処する。他人のために請託した場合も、自ら請託した場合と同じである。主司が法を曲げることに応じた場合、同じ刑に処する。主司が応じなかった場合、主司も請託者も罰しない。法を曲げた場合、主司と請託者をそれぞれ杖100回の刑に処する。法を曲げる罪が重い場合、出入人罪をもって論ぜよ(官司がことさらに軽く又は重く断罪したときの罰則(断獄律19)をそのまま適用する。例えば、徒1年を請求により法を曲げて免除した場合、主司は出入人罪の徒1年に処する)。他人や親族が請託した場合、主司の刑から三等を減じる(ただし、三等を減じた刑が杖100回より軽い場合は杖100回に処する)。自ら請託した場合、本罪に一等を加える。 監臨(支配・監督の地位にある官人)や勢要(監臨の地位にはないが、主司に対して影響力を持つ官人。勢要は、官職が低い者であっても同じである)が、他人のために請託した場合、杖打ち100回の刑に処する。法を曲げる罪が重い場合、主司と同じ刑(出入人罪)に処する。主司が死罪に当たる場合、監臨や勢要は一等を減じる。
[1] およそ公務はすべて正しい道理に従うべきである。もし軽々しく請託し、法を曲げようとする者がいた場合をいう。
[2] 他人のために請託した者は、たとえ自分の事案でなくても、自ら請託した場合と同様に扱われる。
[3] しかし、その請託の内容については
[4] 主官が法を曲げるような請託を許可しなかった場合、請託した者も含め、誰も罪に問われることはない。
[5] もし法を曲げる行為がすでに実行された場合、主官および請託した者はそれぞれ杖刑100回に処される。ただし、本来の罪も依然としてそのまま残る。
[6] 所管の官吏が関係者の請託を受け入れ、不正な判決を下した場合、その罪が百回の杖刑以上の重罪であれば、主官(判決を下す立場の者)は刑の軽減や加重を行った罪に問われる。例えば、もともと一年間の徒刑(強制労働刑)が科されるべき案件において、関係者の請託によって徒刑を免除した場合、主官は徒刑の減免を行った罪に問われ、結果として自身が一年間の徒刑に処されることになる。
[7] もし他人や親族が請託し、その結果として本来の刑罰である徒刑1年が免除された場合、主官(判決を下した者)の罪は3等級減じられ、本来受けるべき刑罰は杖80回となる。これはすでに執行された杖100回の刑罰より軽減される。このような場合はすべて、杖100回を基準として処理される。また、もし他人や親族が請託し、本来2年半の徒刑に処されるべき罪を、主官が不当に判決を操作して免除した場合、請託した者の罪も3等級減じられ、結果として徒刑1年に相当する刑罰となる。このように、減刑の結果として徒刑1年以上の重罪になる場合は、すべて減刑の基準に従って処罰が科される。
[8] もし自ら請託し、その結果として法を曲げることが行われた場合、それぞれ請託による罪に対して一等加えて処罰される。
[9] 監督官を除き、田地を所有する者が官吏である場合、その官位の高低に関わらず制限はない。ただし、主官が畏れを抱き、敢えて違反しない者に限る。
[10] もし他人のために請託し、法を曲げようとする者がいれば、その請託が実行されたか否か、許可されたか否かに関わらず、請託した時点で杖刑100回に処される。もし主官がそれを許可した場合は、笞刑50回に処される。
[11] もし不正行為が杖刑100回を超える重罪に当たる場合は、主官が刑の軽減や加重を行った場合と同様に処罰される。
[12] 主官が処罰として死刑に相当する場合でも、監督官や権勢のある者は死刑より一等減じられる。